医学部の面接
現在、国公私立を問わず全ての大学の医学部入試に面接が採用されている。総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜の、どの選抜方式においても必ず実施されている。医学部入試ではなぜ面接が必須なのだろうか。
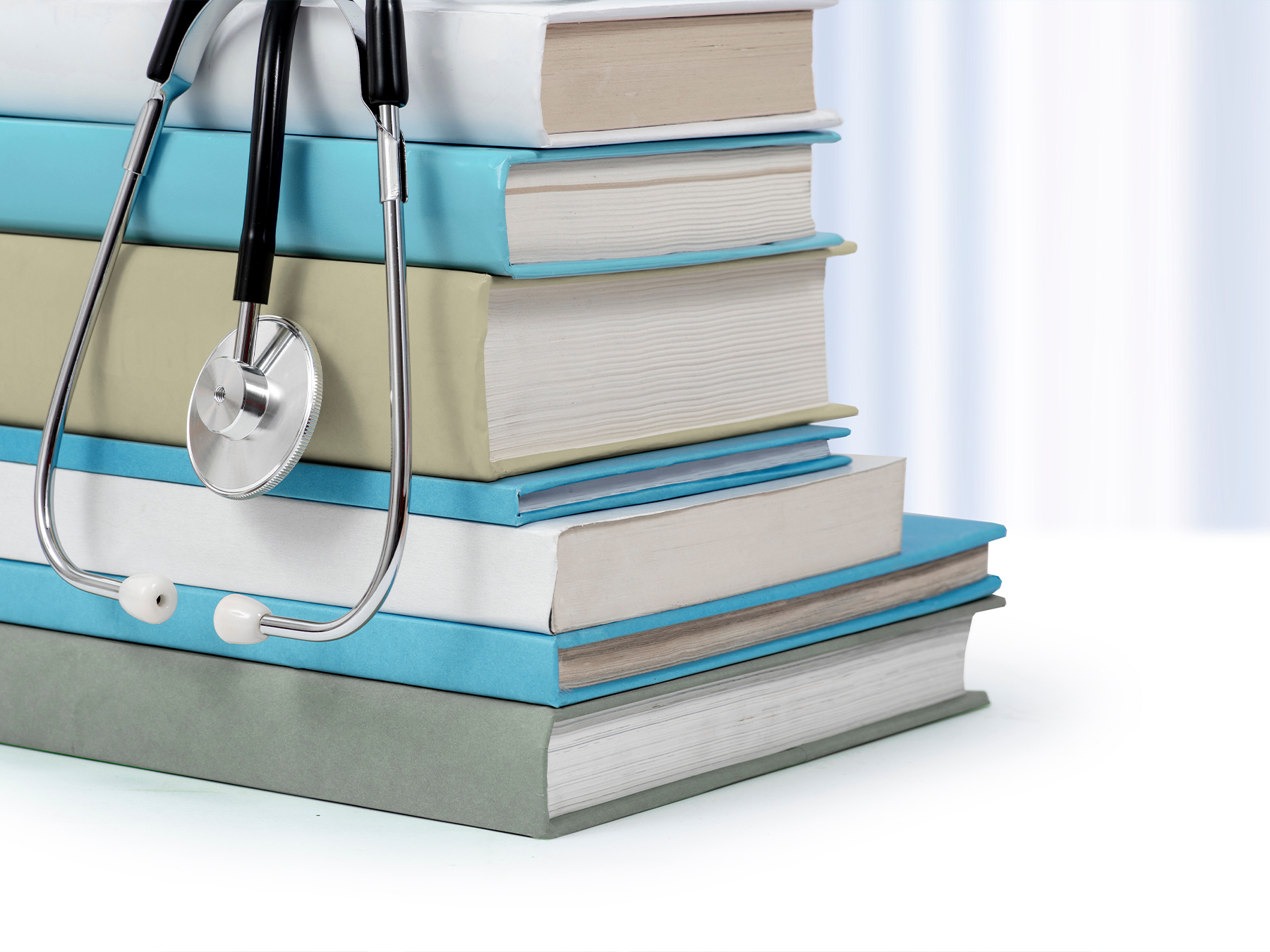
医師としての適性を見る
かつては面接試験のない医学部入試も存在した。それにより、学力は高いけれども適性のない学生が医学部に入学してきた。ミスマッチの学生はやがて適性のなさを自覚し、医学を学ぶ意欲を失い、中退や転学をするケースも結構あったようだ。せっかく教育した学生を医師にできないのは医学部にとって、広い意味で言えば社会にとっても、大きな損失だ。
ミスマッチが起きないように、医師としての適性を見るために、医学部入試では面接を実施する。教科テストの合計がどれほど高得点であっても、医師としての適性を欠く者は面接で不合格となる。また、近年面接の配点を高く設定している大学が増えているので、面接で高得点を挙げれば教科テストの失敗を挽回できる可能性もなくはない。医学部受験において、面接が合否を決め手にもなっているのだ。
医学部の面接で審査される適性は次の4つ(大学によって5つ)と考えてよい。
適性1 高い倫理観を備えている
医師は、病や怪我に苦しむ多くの患者に寄り添う必要がある。そのため、まずは人にやさしくなくてはいけない。人命尊重の精神を備えていることも最低限必要なことだ。
適性2 優れたコミュニケーション能力を備えている
現代の医療は、チーム医療での対応が一般化している。高度化、複雑化した医療に対応するには、専門の科を越えた医師同士の連携、看護師をはじめ多くの医療従事者との協働などにおいて、円滑にチーム医療を進められるコミュニケーション能力が求められる。患者のための適切なインフォームド・コンセントを実現するためにも優れたコミュニケーション能力は欠かせない。
適性3 論理的思考ができる
医師は、筋道を立てて考えて冷静に判断できなくてはいけない。患者への説明、医療チームへの説明も論理的思考に基づいたものでなければ、患者や医療チームに納得感や安心感を与えることはできない。
適性4 課題解決型思考ができる
未知の状況、正解のない課題に対しても、様々な視点から考えを巡らして、より良い解決策を導き出せる。課題解決型思考があってこそ、医学の進歩はあるし、不治の病で苦しむ人の力になれる。また、非常事態が起きても投げ出さずに医療を継続する工夫を考えることができる。
地方の国公立大学、あるいは地域枠の入試を実施している大学では、次の点も受け入れる学生に求められる大切な適性である。
適性5 地域医療に貢献する意思がある
地域の医療に貢献したいという意思をぶれずに伝える必要がある。「僻地に○年」「地域の医療機関に○年以上」といった出願条件が募集要項に記載されているはずだが、その条件を受け入れる覚悟をしっかり示さなくてはいけない。また地域に関する基本情報、地域の医療環境なども頭に入れておくほうがよい。
適性を見抜くための面接形式MMI
医学部の面接は、個人面接、グループ面接、ディスカッション、MMI(マルチプル・ミニ・インタビュー)の4つの形式で行われることがある。大学によっては、個人面接を2回、あるいは、個人面接とディスカッションの2パターンを実施するなど、複数回の面接を実施することもある。
ここでは、医学部面接で特有の形式であるMMIを紹介する。
MMIは複数の個人面接を連続して行う形式だ。面接会場がいくつかの席に区分けされて、各所で面接官が待ち受けている。健康診断であちこち検査しながら診察場所を移動するのに似ている。各席でそれぞれの面接官から質問を受ける。大学により様々だが、志望理由、高校時代に最も力を入れたこと、時事問題などのよくある質問を受ける場合もあるが、紙に書かれた課題を渡されて「もしも~話」の回答を求められることもある。各席での時間は10分以内の短い面接だ。MMIは、考える間を与えずに連続して面接をすることで、受験生の本音も出やすい。まさに適性を見抜く目的で工夫された面接形式と言えよう。
医学部の面接対策のさらに詳しい解説は『総合・推薦入試 面接で逆転合格』(和田圭史著・Gakken)を参照してほしい。
