メリハリのある読書感想文を
書くために
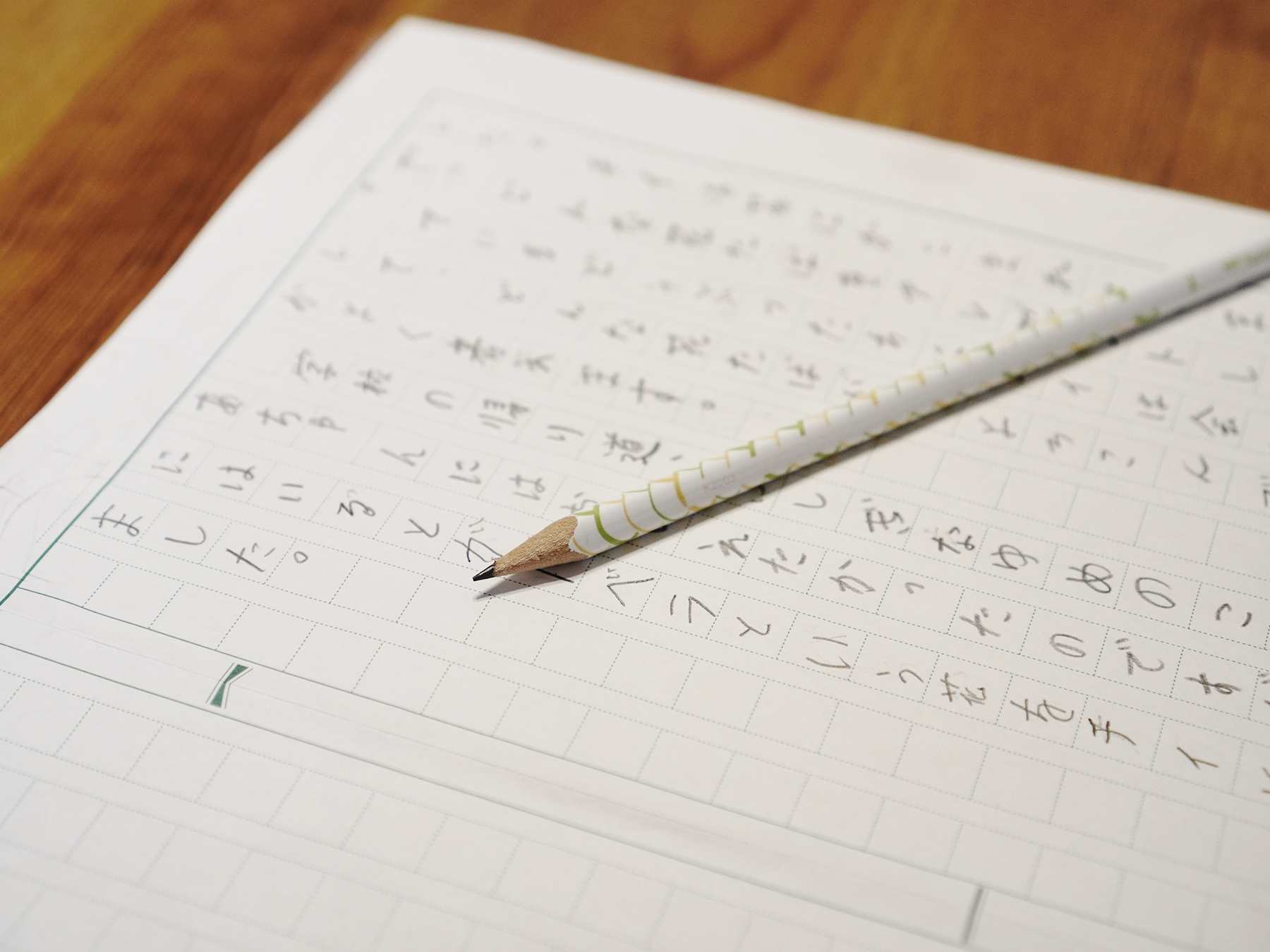
一昔前まで、夏の宿題の定番と言えば、読書感想文だった。しかし、最近は読書感想文の宿題を出さない学校も増えてきているようだ。白藍塾小学生作文教室では、夏になると2回だけの特別講座「読書感想文クラブ」を開講する。以前は圧倒的に夏休みの宿題対策で受講されるお子さんが多かったが、最近はそれだけでなく、作文を書かせる機会と本を読む機会の両方を得られる読書感想文講座をぜひ子どもに体験させたいと、学校の宿題とは関係なく、ご家庭の判断で受講を申し込まれるケースも増えているようだ。
本コラムでは、白藍塾流の読書感想文の書き方とともに、どうすればよい読書感想文が書けるか、そのツボを紹介したい。
メリハリのある読書感想文を書くために
白藍塾では、次の四部構成で読書感想文をまとめるように教えている。
ホップ
最初に本を手にとったときの印象や本を読むことになったきっかけを書く。
ステップ
本の内容を簡単に説明する。物語などの場合は、あらすじを書く。ただし、感想文はあらすじ紹介が主ではないので、簡単に説明する程度で十分。
ジャンプ
その本のどんなところがおもしろかったか、それを読んで何を考えたかを、なるべく個性的に書く。ここが読書感想文の中心。
着地
全体をまとめる。これからどんなことを考えていきたいか、どんなことをしたいか、さらにどんな本を読みたいかを加えるのもよい。
もちろん、優れたお子さんであれば、独自の書き方でも立派な読書感想文が書けるだろう。しかし、多くのお子さんは、だらだらと本の内容をなぞり、最後の最後で「私もこれからは・・・のように、友達を大切にしたいと思います」などと、教訓めいた感想をひと言添えるだけのつまらない感想文を書いてしまう。「ホップ」「ステップ」「ジャンプ」「着地」の4つのブロックを意識して、どこに何を書けばよいかを考えながら書くことで、メリハリのある読書感想文を書けるようになる。
メインテーマをさがす
読書感想文で最も重要なのは「ジャンプに何を書くか」だ。読んだ人に「鋭いなあ」「深いなあ」と感心してもらうには、本のメインテーマをどう捉えるかがカギになる。メインテーマとは、本を通して作者が一番言いたかったことだ。評論文の場合は、書き手の主張はひとつで捉えやすい。しかし、物語は、優れた作品であればあるほど、多面的な読み方ができて、主張を捉えにくいものだ。それでも、文中のいくつかの手掛かりからメインテーマを探り出し、それに対する自分の考えを述べることで、優れた読書感想文に仕上げられる。
読書感想文を書くために、「果たしてメインテーマは何だろう」と考えながら読む行為は、探偵が犯人を割り出す推理の過程に似ている。メインテーマを探るには、物語のターニングポイントはどこか、クライマックスでは何が起こったか、登場人物の関係性はどうなっているか、といった文中に残された「証拠」をひとつひとつ辿っていくことが重要だ。そのひとつひとつの証拠を子どもたち自身が発見できるようにサポートするのが白藍塾の実践する読書感想文指導である。
詳しくはこちらを見てほしい。
別の読み方も許容する
定めたメインテーマとは違う捉え方をする子どもも当然いる。明らかに間違えた捉え方をしている場合を除き、指導者はできるかぎり、一人一人のお子さんの独自の読み方を許容することも大切だ。そのうえで、もうひとつの読み方があることを示唆し、定めたメインテーマを考えさせるように仕向けられれば、多様な見方も育てられて、さらに意義ある学習になるだろう。
メインテーマ会議を家族で
蛇足ながら、ご家庭でメインテーマ会議を開くことをすすめたい。お子さんの読んだ本を家族で回し読みをした後に開くとよい。
当塾で読書感想文指導を行う際には、課題図書のメインテーマについて講師間で共通認識を持つための会議を開くことがある。これが中々まとまらない。しかし、会議で講師たちが丁々発止と渡り合うさまは見ものではある。刑事ドラマの犯人捜しの捜査会議をしているような気分を味わえるからだろう。熱くなりながらも、どこか議論を楽しんでいるようなところがある。ぜひご家庭でも、お子さんの読書感想文執筆を機会に、白熱したメインテーマ会議を開くことをすすめたい。ご家族の意外なものの見方や深い洞察力を知る機会になるかもしれない。
